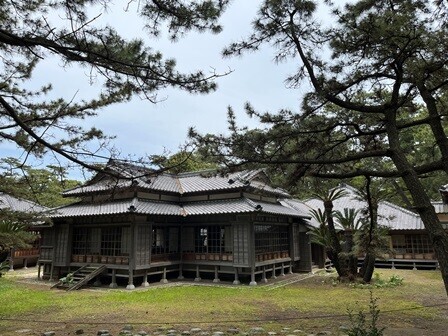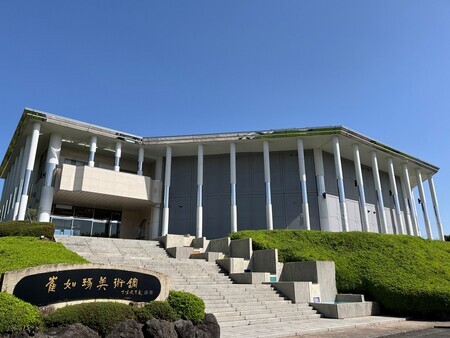ここ数年、テレビで取り上げられることも多く、毎年妻が「行きたい、行きたい」と宣う。前日、夜中に調べると高速を使うとだいたい2時間と少しでいける計算。単純に11時に家を出れば1時過ぎには着く。たぶん土日は物凄く混雑するだろうから、行くならウィークデイ、妻のデイサービスが休みの木曜かと。
前日、明け方近くまでビデオ講義をまとめて受講していたけど、なんとか10時頃に起床。支度してから階下に降りて出かける旨を伝え、妻のインシュリンをうってから出発。なんだかんだで家を出たのは11時過ぎ。家の近くのコンビニでおにぎりとかを買ってから高速にのったのは11時半頃。ナビの到着時間は1時35分と出た。
道順はナビまかせで、圏央道から東北道に入り北関東道へとなる。東北道から北関東道は、以前よく日光の帰りに水戸や笠間の美術館に行くときに使ったコースだ。途中、笠間のPAで休憩を取ったのでひたち海浜公園ICを降り無事到着したのは2時くらい。閉園が5時なので正味3時間。とにかく広大なスペースなので、目的のネモフィラとやはり見頃というチューリップを見ることが出来ればいいかとアバウトに考える。
しかしウィークデイなのにかなりの人出だ。自分らの高齢組も多いけど、若いカップルも沢山来ている。そしてインバウンド組。ガイドが旗を持って先導する団体ツアー組は、中国とか台湾とかそのへんが多い。昭和時代、東南アジアに沢山繰り出した農協ツアーとかそういうのって、みんなこんな感じだったんだろうか。まあいいか。
たまたま入ったのが西ゲートの駐車場だったのだが、これは正解。ネモフィラは西ゲートからだいたい徒歩で15分くらい。バスでピストン輸送もしているようで、そこの係のおじさんに歩くとどのくらいかと聞くと、「20分くらい」との答えだったけど、そこまではかからない。こちらが車椅子なので、少し多めにみたのかもしれない。
西口ゲートの門はなんていうか、スタウォーズのスター・デストロイアーを思わせるような感じ。

そして門を抜けるとこんな感じで風景が広がる。ネモフィラは左奥をずっといく。チューリップは右側。さらにずっと右側に中央ゲートと遊園地がある。

真ん中には池があるのだけど、逆から見るとこのように。

ネモフィラみはらしの丘
そしてぞろぞろとネモフィラのあるみはらしの丘を目指す。
なかなか壮観な光景が目の前に広がる。



丘を目指すの人の列に加わる。頂上への道は上るのと下るのが別れているのでさほどの渋滞感はないけど、それでも人が多い。みんな思い思いに写真を撮っている。
予想はしていたけど、この丘を車椅子押して上るのはけっこうしんどい。数十メートル上るだけでふくらはぎがパンパンになってくる。勾配はさほどきついわけではないけど、とにかく延々とくねくね道が続く。「ロング・ワイディング・ロード」ってこういうものか。
途中で休み休みしながらこちらも写真をとったり。

頂上付近は人の滞留も多くごった返している。でも写真を撮る人たちが二重、三重とまではいかない。少し待てば前列にも行ける。けっこう譲り合うような感じ。団体中国人ツアーも写真を撮るのに夢中な人もいれば、こっち空いてるよとスペース開けてくれる人もいたりする。若いカップルたちも車椅子の我々に親切にしてくれる。美しい景色に接すると、割とみんな余裕が生まれるのだろうか。みはらしの丘にいる限り、世界は平和というところだ。







菜の花畑
ネモフィラの丘を降りると、菜の花畑がある。菜の花もなかなか見事に咲いている。薄い青から黄色の世界へ。



チューリップ
みはらしの丘から来た道を戻って西池のほとりを迂回するとたまごの森フラワーガーデンに着く。そこがチューリップの見頃後半ということでいろいろな種類のチューリップがキレイに咲いている。見頃後半ということで多少花が開きかけているけれど、単色のネモフィラよりも、こっちの方が色鮮やかでインパクトがある。まさに絵に描いたみたいな感じ。










遊園地エリア
時計を見ると時間は4時くらい。あと1時間なのであまり遠くまではいけないけど、とりあえず中央広場と遊園地の方に行ってみることにする。できれば観覧者くらいは乗りたいと。
西口エリアから中央ゲート方面には遊歩道を通っていくのだけど、途中に橋が二つある。一つがそよかぜ橋でもう一つがまつかぜ橋。橋の下には常陸那珂有料道路が走っている。
そよかぜ橋を渡ってテクテクと車椅子を押してのんびり移動。もう閉園時間も近いので観覧車も空いている。近くの乗り物券の自販機でチケットを購入。一人600円也。車椅子ごとゴンドラに乗るタイプもあるのだが、けっこう待つみたいなので、通常のゴンドラに乗ることにする。妻は動いているゴンドラに乗るのは難しいので、一時的に観覧車をとめてもらう。有難い。
観覧車は一周15分くらい。真下の風景やら遠くのネモフィラの丘を見たりとゆったりと見学。高い所はダメな方だが、観覧者はまだ大丈夫か。ゴンドラによっては足元がスケルトンという胡乱なものもあるらしいが、それは多分絶対ダメだと思う。
4年前にアナハイムのカルフォルニア・アドベンチャーで乗った観覧車は、ゴンドラが揺れるわ内側にスライドするわで、家族の前で「ごめんなさい」を連発し、おまけに酷い乗り物酔いになったことがある。日本の観覧車は平和。



観覧車を降りてからは休憩タイム。ネモフィラ・ヨーグルト・ソフトという、いかにも身体に悪そうな着色のソフトを食した。

閉園までの時間も少なくなったので、大草原エリアの脇の遊歩道を通ってまつかぜ橋を渡り、ふたたび西池の周囲を周回しながら西口ゲートに戻った。
ウィークデイでそれなりに人出も多かったけど、それでもまあまあゆったりと花を見て、心地よい時間を過ごせた。多分、土日はとんでもない混み方をするのだろうとは思う。駐車場を出るまでに要したのは10分程度だが、あちこちに混雑しているときには1時間程度要するとの掲示もあった。これからゴールデンウィークは物凄いことになるのだろうとは思った。
埼玉からひたちなかはけっこう遠い。今回思い立ったのは、来年、再来年と年を経れば、なかなか遠出もしんどくなるだろうし、車椅子を押して丘を登るのもきついだろう。それを思うと、行くなら「今でしょ」みたいなギリ、ワンチャンみたいなことを思ったからでもある。年取ると、なにをするにしても、そういうことを考える。淋しいことだけど。
家に帰ってからちょっと調べてみると、この国営ひたちなか海浜公園はもともと陸軍水戸飛行場だったところ。戦後はアメリカ軍に接収されて射撃場として使われていたのだとか。返還されたのは1973年、沖縄返還の翌年のことだ。公園としての事業に着手したのが1979年。けっこう現代史なのだなと思ったりもした。